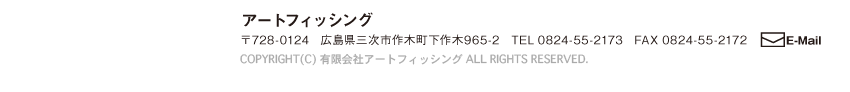開高さんからの手紙
銀山湖で58cmの悪魔を釣り上げた後、常見はますますルアーフィッシングの魅力に取り憑かれていく。翌年の1968年は、なんと100日以上も銀山湖へ通った。
そして木枯らしが吹き始めた11月下旬、常見の元に一通の手紙が届く。その主こそが作家・開高健であった。
文面によると、開高は西ドイツを旅している時に、釣り具店の主人からルアーフィッシングを教えられ、湖でノーザンパイクを釣り上げる。これですっかりルアーの虜となった開高は、帰国後あらゆる資料を集め、その中で一つの記事が目に止まった。それは、常見が先の大イワナ釣りの模様をまとめたもので、『湖の疑似バリ釣り』と題して雑誌『つり人』に発表したものであった。手紙には「……ついては、どうぞ釣り場などモロモロをご教授願えないものだろうか」と記されていた。
開高さんとの出会い
早速、常見は兄と二人で、神田のお茶の水にある「駿台荘」を訪ねる。ここで開高は原稿の執筆をしていたのだ。
「開高さんは、黒のトックリセーターを着ていて、第一印象は目の澄んだ人だなと思いました。そして、目の中に釣り師だけが持っている特別な光を感じたんです」
緊張が解けたあとは、たちまち釣り談義に花が咲いた。その時、村杉の佐藤進氏が釣り上げたイワナの写真を見せると、開高さんは「ホッホー!」と大きな声を上げた後無言になった。そしてこの時、一緒に銀山湖を訪れることを約束したのだった。
その約束が実現するのは、1970年の春のこと。前年の3月に丸沼へ行き、開高は65センチのニジマスを釣り、「ブラボー」と叫んだという逸話が残っているが、その後銀山湖へ行こうとした時、『フィッシュ・オン』の取材で世界を回るためになったため、一年遅れての初釣行となった。この時の模様は、その後『フィッシュ・オン』に掲載され、「名人と上手と鬼と巨匠」というキャプションが入った秋元啓一氏の写真はあまりにも有名である。
「この時開高さんが狙っていたのは60センチオーバーのイワナです。でも私は釣れたんですけど、開高さんは釣れなかったんですよね。それが悔しかったんでしょう。小説の執筆もあったと思いますが、村杉小屋にこもって一人で釣りをしていましたから。そして58.5センチが釣れた。フィッシュオンの最終章にある通りです」
バイトの誕生
その後も、常見と開高健との交友は続き、ビデオエッセイ『河は眠らない』の収録では、アラスカに同行したり、モンゴルのイトウ狙いでは、先発隊としてチョロート・ゴルへも出掛けたりした。そして、国産スプーンの元祖として知られる『Bite(バイト)』も、そうした交友のなかから生まれた名品である。
そもそも常見がバイトを作ろうと思ったきっかけは、市場からルアーが消えたことにある。銀山湖で鮭のような魚が釣れるという事実が世に広まると、釣り人たちはこぞって奥只見を目指した。その数実に3万人以上というから、驚きである。
それに伴って、ルアーフィッシングの人気も急速に高まりつつあった。釣り具店にあったルアーはあっという間に姿を消し、どこも欠品状態。『トビー』や『オークラ』といった人気のスプーンは、ほとんど手に入らなくなった。
「今とは違って、もともとルアーを売っているお店自体が少なかったので、本当に手に入らなくなりました。東京のつるや釣具店なんかでは、全部買い占めてしまう人もいるぐらいで、その盛り上がり方はすごかったですね」
困った常見は、ここである決意をする。「なければ自分でルアーを作ってやろう」と思ったのである。
厚さ1ミリ程度の銅板を購入して、それを金鋏で切り取って、トンカチで叩き、膨らませたり、へこませたりしながらスプーンの形にしていく。出来上がったスプーンは、塗装もせずにそのまま釣り場で投げてみる。気に入らなければ戻って再びトンカチで叩く。その繰り返しだった。
「いや〜、今思い出しても不思議ですね。本当に数えきれないぐらいのスプーンを作りました。あの頃の情熱が今はただ懐かしいです」
こうして生まれたのが『Bite(バイト)』だった。名付け親は開高健。第一次ルアーブームの最中、1973年のことである。